というわけで…紹介する順番がバラバラになってしまうかもしれませんが…過去に発行されたジオルジュです!
2022年前期 2025年4月6日更新!
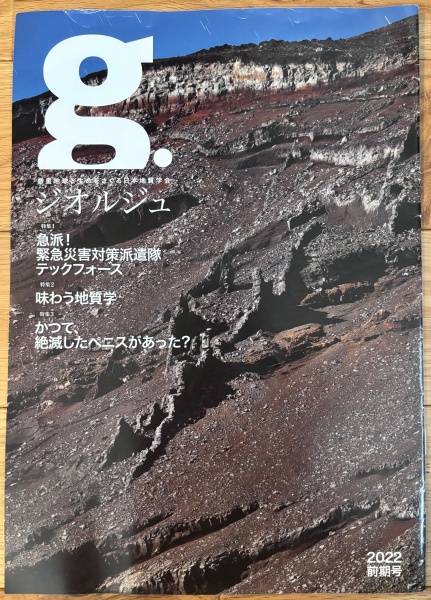
緊急災害対策派遣隊
災害があった時の報道などで、警察や消防、そして自衛隊の皆さんが活躍しているのを見ることがありますが…実は、それ以外にも現地で活躍している方々がいたんですね~。知らなかったです。
それが、「国土交通省の緊急災害対策派遣隊」なんだそうです!
この緊急災害対策派遣隊…通称テックフォースと言うそうですが…具体的にどんなことをしているのかというと…二次災害が起きないように技術的な支援をするチームなんだそうです。
災害が起きた時、人命の救助には一刻を争う場合があります。そういった場合に、迅速に活動できるためには、助けに行く側が災害に遭遇しないためにどうすべきか…といった判断、支援についてのスペシャリストなわけです。
私たちが普段、テレビなどでみるのは自衛隊や消防の活動の様子かもしれません、しかし、自衛隊や消防が安全に活動できるのは…こういった人たちのサポートがあったからんなですね~。いや~知らなかったです。すべての災害において、こういった緊急災害対策派遣隊が存在するのかどうかはわかりませんが、裏方として活躍している人たちがいるというのを知ることは大切なことだな~っとおもいます。ありがとうございます!
味わう地質学
毎日新聞の夕刊に「美食地質学入門」というのが掲載されて「いる」のか、「いた」のかはわかりませんが…そういった連載があったようです。
地質学と料理って関係あるの?と疑問に思ってしまいますが…よ~く考えてみると、「料理に使う素材は、土地の影響を受ける」ということであれば、土地の「質」が重要になってくると考えれば、地質学が料理に影響もするでしょうね~。
今回の特集で紹介しているのは…ごぼう! おいしいよね~。
かつて、絶滅した〇〇〇があった?
ん~。これ…書いていいのか…微妙…。学術的な事だったら…いいのかな~。
詳しくは、上記の写真にて…確認してください。
ワタクシは、少なからず生物の進化というものに興味があり、「なぜなのか、どうしてなのか」という事を知りたいと思っています。ただ、進化というものを見るときに、どこに焦点をあててみるか…という部分において、今回は目から鱗が落ちた感じがします。
もともと…陸上に生物がいない状態で、海の中でのみ生物が活動していたとすると、繁殖の方法というのは今とあまり変わらないはず。しかし、この時に、すでに卵生か胎生かという違いが生じていたかもしれない…この繁殖の方法と進化の過程というのは…非常に興味深いことだな~っと思いますが…そんなことを考えさせる記事です。
銚子ジオパーク
銚子ジオパークが紹介されています!
行ったことないんですが…行ってみたいですね~。あ、海水浴には行ったことあります!
ジオルジュ・コラム
宝石も…地質学なんでしょうかね~。誕生石というのがありますよね~。これが…増えたそうです。
ん~。ま、色々あるんでしょう。ちなみに、ワタクシは2月生まれですので…誕生石というと、アメジストが有名ですが…この度、クリソベリル・キャッツ・アイという宝石も、2月に認定されたそうです!
ただ、これは日本だけの事かもしれないので…世界的にどうか…と言われると…わかりません!
2022年後期

来るなら来なさい南海地震 高知県民の覚悟
すごいタイトルだな~っと思って記事を読みました。日本地図をみれば、高知県は太平洋側に面しており、30年以内に7割から8割の確率で来るといわれている南海地震での津波をもろに受けるということになります。
もちろん、防潮堤などのインフラ整備も大切なことではありますが…県内全域となると…時間がかかります。その間に、津波が来てしまうことを想定して、命をまもるために逃げる訓練というのを徹底して行っているそうです。その中心的な役割をになっているのが…こどもたちです。
抜き打ちで行われる避難訓練で、与えられた情報から、どこに逃げるかをこどもたちが考え、街中を全速力で走り抜ける…。そんなこども達の姿をみたら、大人は黙っていられますかいな。こども達のために何が必要か考えるでしょうね~。すごい取り組みだと思います。
東日本でも、昔からの言い伝えや語り継がれた情報で命が助かったということがありました。こういった、いつ来るかわからない災害にそなえるのは、平常時の意識。高知県の取り組みが全国に広がることを願わずにはいられませんね。
温泉水を煮詰めてつくる「会津山塩」
福島県出身でありながら…会津山塩?聞いたことないな~っと思っていましたが、それもそのはず、最後に作られたのは…1948年ころのこと、そして商工会を中心に復活したのが2005年ということで…まぁ、知らなくてもしょうがないわけですが…。
磐梯山の温泉水から塩をつくっていたという歴史があるんですね~。会津といえば…内陸で太平洋からも日本海からも遠いので、こういった手法で塩を確保していたということなんですね~知らなかった。当然…江戸時代だと会津藩の皆様も食べていたと思いますし…どうなんでしょう。同じ温泉があった藩は、同じように塩を作っていたんじゃないですかね~。そういった人間が生きていくうえで必要な塩という視点で歴史や藩の経済をみていくのも面白いかもしれませんね~。
現在も…販売しているようなので…食べてみたいですね~。
漂流する軽石
こちらは、ニュースにもなりましたので、ご存知の方も多いと思います。海底火山の噴火により、大量の軽石が生成され、太平洋沿岸部に大量に漂着してしまい被害がでたというものです。
まぁ~、自然のやることですから…どうしようもないと言えばそうですし…噴火は防げませんし、対応していくしかないわけですよね~。
研究×技術×デザイン
つくば市にある産業技術総合研究所地質調査総合センターの博物館のミュージアムショップでは、ここでしか買えないグッズを、研究者と技術者とデザイナーが協力してつくるという試みを行っているそうです。
グッズは、標本館に来てもらうことを目的としているので、ネット販売とかはしていないそうです。もぅ、行かなきゃ買えないというわけですが…そのグッズがすごい!
研究の成果と、どんな岩石や化石でも0.03ミリメートルの薄さに切り出してしまう技術に、デザイナー視点が加わることで、すごいグッズが生まれています。冊子には、写真も掲載されていますが…欲しい!と思ってしまうものばかり、どんなグッズがあるのかは…地質標本館のHPでみることができますので、ご覧ください。
地質標本館の公式HPはコチラ → かなり…いいよ!
お値段も…そんなに高くない!
南紀熊野ジオパーク
南紀熊野のジオパークの紹介記事が掲載されていますが…すごいですね~。行ってみたい!
地球科学者は語る Vol.20
Vol.20とありますが…ワタクシは、このコラムを読むのは初めてです。毎回というわけではないんですね~。今回は、海洋堂の造型師・塗装師の古田さんとの対談が掲載されています。
もう、海洋堂といえば…フィギュアで有名ですものね~。ぜったい、どこの家にも1体はあると思います。
2022後期 まとめ
というわけで、2022後期号を紹介してきました。他にも、ジオルジュコラムや、NPO法人地学オリンピック日本委員会の…これは宣伝だったのかな…。色々な記事がありまして、楽しく読ませていただきました~。
ありがとうございました~。



コメント